| 眼鏡の日本伝来と変遷 |
1.眼鏡の渡来
16世紀中ごろにポルトガル人が種子島に上陸して、日本に鉄砲を伝えた頃の日本に眼鏡が伝来している。『大内義隆記』に
「都督在世の間より石見国に銀山が出来て宝の山となりけり。異朝より是れ聞き唐、天竺、高麗の船数々渡す。天竺人の贈り物様々な中に、老眼のあざやかに見ゆる鏡のかげなれば、程遠けれどもくもりなき鏡二面候えば、かかる不思議の重宝を王様に贈りけるとかや云々」。
この記録の「程遠けれどもくもりなき鏡」とは姿見鏡で、「老眼のあざやかに見ゆる鏡」とは老眼鏡と推定される。「王様」とは大内義隆とも朝廷の天皇とも思われるが、時代から考えて時の権力者の室町将軍であった足利義晴をさすであろう。
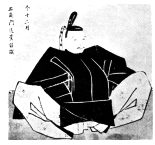

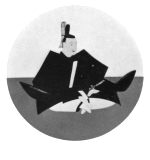
日本にキリスト教を伝えたというフランシスコ・ザビエルが天文18年<1549>が周防国山口に来て、ときの領主大内義隆に布教の許可を得るために種々の贈り物をしたという。府内こと大分市にて布教を開始し、京都にても将軍に面会し、掛眼鏡を贈ったとポルトガル宣教師ルイス・フロイスの『日本誌』に記載されている。すなわち、「ここに於いて彼(ザビエル)は彼(大内義隆)に13種の貴重なる贈り物…麗しき水晶 瑠璃、鏡、掛眼鏡…」とある。
ザビエルが用意したプレゼントは、ポルトガル印度総督が準備したものであって、このことからポルトガルが日本進攻するためで、ザビエルが日本偵察のために派遣されたスパイであったという説もある。
ここ最近までの日本最古の眼鏡は、徳川家康を祀った久能山東照宮の宝物殿の眼鏡といわれていたが、前述のことから、眼鏡研究家として著名な大坪元治氏が京都紫野〈京都市北区〉の大徳寺に所蔵されていた眼鏡を発見し、歴史が覆されることとなった。この眼鏡は象牙製瓢箪形で、クサビ付きの開閉できる容器に収められる折畳み式の鼻眼鏡で、枠は亀甲のように見える。
日本最古と称していた徳川家康が所持したという眼鏡は、江戸初期にスペイン領フィリピンからスペイン領メキシコに航海中であったセバスチャン・ビスカイノが漂流して日本に着岸したときに、家康が船を修理させメキシコへ到着するための薪水や食料を援助したことに由来する。援助謝礼に慶長18年〈1613〉ビスカイノが来日して、徳川家康に差し出した土産のひとつが、亀甲のフレーム製の無関節式鼻眼鏡であった。
2.織田信長と眼鏡
織田信長が岐阜城にいた頃の話として、
『吉利支丹〈きりしたん〉物語』に伴天連〈ばてれん〉と称せられたイタリアの宣教師オルガンチノがフランシスコ・ガブラルを同伴し岐阜を訪問した折りに、ガブラルが眼鏡を掛けていたので、四ツ目の怪物とあって、数千の群衆が見物したとある。すなわち「師父フランシスコは近眼視なりき彼が土地の状況を見んがため、「眼鏡」をかけたり。この眼鏡について人々の驚きはたとえようもなく大なりき。バテレン四個の眼を有す、二個はすべての人の自然にあるべき所にあれども、他の二つはそれより少なく離れて外側にあり、鏡のごとく輝きて見るからに恐ろし」とある。

【参考】『南蛮寺興廃記』には、伴天連ウルガンの献上品の中に「75里を一目に見る遠眼鏡」とか「茄子が卵のごとく見える眼鏡」があったという記録がある。
3.江戸時代へ
ポルトガル船が日本にはじめて鹿児島に来航したのが、天文13年〈1544〉で、ザビエルが来日したのが天文18年であった。老眼鏡が初めて日本に持ち込まれ、翌年には京都にて室町幕府将軍の足利義晴に眼鏡が献上された。この眼鏡はポルトガル印度提督が用意したものであった。
戦国時代の中から、織田信長は天下布武を旗印にして、足利義昭を天正元年〈1573〉足利将軍にして、全国統一をめざした。壮大な安土城を建設し、関所を廃止し、楽市楽座などを実施したが、いわゆる「本能寺の変」で明智光秀に討たれ、信長の天下統一の目的は挫折した。この間に、南蛮貿易やキリスト教布教により眼鏡の存在が広まっていった。
信長の志をついだ豊臣秀吉によって、全国制覇が達成された。秀吉の領土欲は、琉球・台湾・フィリピンにまで及び、朝鮮・明国をも従えようとした。イスパニアやポルトガルのアジア進出で西欧文化が普及しており、眼鏡も伝えられていたようだが、必要性が低かったことから生活の中への取り入れは無かった。 慶長5年〈1600〉徳川家康が関ケ原の合戦で石田三成軍を破り、全国支配権を手中にし江戸幕府を開いた。3代将軍徳川家光は幕府への忠誠を強める目的で切支丹弾圧に走り、鎖国政策へと進んだ。
長崎領主の松浦氏は、江戸幕府の命令に従って長崎平戸を指定港として、ポルトガルと交易していたが、寛永17年〈1640〉宗教問題から交易はキリスト教布教には消極的であったオランダに限定された。この交易は長崎出島に移り、長崎が文明開花の窓口となった。
1.江戸時代の対外交渉
徳川家康による江戸幕府は鎖国政策をとり、外国との交渉はオランダ1国に限定したのである。オランダとの貿易は平戸から長崎出島に移り、長崎が文明開化の窓口となった。シーボルト・お瀧で有名な鳴瀧塾をめざして蘭学を志す若者が集まったことは周知といえる。そこで新しい医学が芽をのばし、眼鏡の製作もまず長崎に根を張った。当時、オランダは眼鏡の先進国であった。
【参考】シーボルト〈1796〜1866〉は、ドイツ人医師で博物学者。
1823年オランダ商館付医師として来日し、鳴瀧塾で医学を教授して蘭学発展に貢献。5年後の帰国時に、日本地図持ち出しというシーボルト事件を起こす。1859年にオランダ商事会社顧問として再来日し、3年後に帰国。息子も来日し、日本外交の手助けをしている。
楠本たき〈1807〜1869〉は、シーボルトの世話係として出島にはいり、4年後に楠本いねを産む。シーボルトの『日本植物誌』に「ハイドランゲア・オタクサ」という紫陽花は「おたきさん」の名からとったもの。
2.洋式眼鏡製造の嚆矢か? 浜田弥兵衛・・・『長崎夜話草』の記述から
「長崎住人、浜田弥兵衛というもの、壮年の頃、蛮国に渡り眼鏡造り様を習い伝えて来りて、生島藤七と云う者に教えて造らしめる」と『長崎夜話草』にあり。
浜田弥兵衛は、長崎の貿易商末次平蔵の配下船長で、鎖国政策前から海外貿易に従事していた。ある時、弥兵衛の船が台湾に寄港した時にオランダ台湾総督ピーター・ヌイツにより弥兵衛の船の武器が押収された。この報復に台湾へ航行し、ピーター・ヌイツを降伏させ、以前の賠償金を受け取りあわせて眼鏡製造技術を習得する機会を得て、長崎に帰帆したという。長崎にて、生島藤七にその技術を伝えたともいう。
よって、浜田弥兵衛は洋式眼鏡製造技術紹介の嚆矢といえよう。
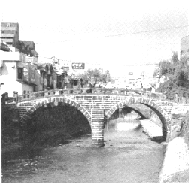 (文献5より) |
1634年(寛永11)長崎に出島が築かれた時に来日した明の僧侶黙子如定は、現在の長崎の顔でもある眼鏡橋の築造法を日本に伝え、その指導をして造らしめている。これとともに、眼鏡製作法を教えたとも伝えられている。中国式眼鏡いわゆる支那眼鏡という大玉のレンズ研磨法である。 |
4.モンタヌスの『日本誌』から
「小田原候にして天文学者なる稲葉美濃守様より優等の望遠鏡2個の希望あり、閣員の松平伊勢守は懐中鏡5個、読書鏡5枚、眼鏡3個、エンペロル(筆者註〜将軍のこと、天皇と間違えている)の叔父水戸中納言様、鏡3個の希望あり、すべて此等には其の希望の品を献ずるなり」
民間にも需要が増したとみえ、長崎あたりには、1661年(寛文1)には立派な眼鏡店があったと『長崎夜話草』に記載され、京阪地区にも専門店があらわれはじめている。
このように、寛永以後の長崎には、洋式および支那式二様の眼鏡製作法が移植され、日時を経るとともに国内諸国に伝えられたのである。
長崎の眼鏡橋はまことに眼鏡発祥の地にふさわしい記念の橋というよう。長崎出島から入った西欧文化は京都・大坂そして江戸へと伝わったのである。この経緯を『長崎先民伝工芸資料』は、
「日眼鏡、月眼鏡(眩しからざる眼鏡なり)、遠眼鏡、虫眼鏡、近視眼鏡等なりを既にして京都および大坂、江戸の工人もまた是れを作る。長崎の巧みを伝うるなり。而してのち、長崎および京都、大坂、江戸の工人店をひさぐ。また硝子をもって数珠、鏡、眼鏡等の器物を作ること盛んなり。工人各店を開くに至れり。これを玉屋也という。業をつたえて今に至る」
と記している。
1.眼鏡研磨技術の発展
『工芸資料』が説くように、寛永(1624〜1643)以降、長崎に起こった洋式および中国式眼鏡製造技術は、まもなく京都・大坂・江戸その他の都市に伝播し、発達していった。
この江戸時代中期における眼鏡製造業は、眼鏡の主要部分であるレンズの研磨という点では、好条件に恵まれていた。というのは、わが国には古代の大和朝廷の頃に、当時の重要な装飾品たる曲玉を研いた「玉造」という職業があった。三種の神器のひとつである八尺瓊曲玉(やさかにのまがたま)を作りあげていたのである。この玉造の伝統が残っていて、その技術がレンズを磨くに役立ったのである。古代社会の玉類の原料は、翡翠・瑪瑙・水晶のほかに出雲地方産のガラスが使用されたであろう。出雲のガラスとは、『延喜式』に「大和朝廷に美保岐玉を献じた」とある記述から、また、正倉院の御物かガラス製の壷・盃・数珠などが遺存するように、わが国のガラス製造はかなり古いようである。南蛮貿易が盛んとなり、ガラスが輸入され始めると、古代技法に基づいてわが国にてもガラス製造が行なわれるようになった。江戸時代中期では、ガラスはビードロとかギャマンと称しており、珠玉を材料にして磨いてレンズを作り上げていたようである。
儒医として有名な黒川道祐が著した『雍州府志』に眼鏡に関して玉石具の稿に、
「御幸町三条の北に玉人多し。水精並びに珍石を金剛砂を以て磨耗、雑品物を作る。是玉屋という金剛砂は大和国金剛山より出ず。」
とある。
これと前後して1690年(元禄3)に出版された『人倫訓蒙図彙』の玉磨の項目に
「珠摺、眼鏡、数珠粒は水晶を以て作れり。金剛砂に水を垂らして鉄の桶にあて是れを摺るなり」とあり、この記事の挿し絵にガラス器を製造中の工人が描かれ、眼鏡レンズが描かれている。
三宅他来によって著された『万金産業袋』には、
「常に用ゆるの眼鏡、若年、中年、老年の分かちあり。若年は玉うすくみな硝子なり。中年より段々老年にいたるほど玉厚く、本水晶を用う。」
ともある。
眼鏡製造法については、1713年(正徳3)に刊行された寺島良安編集の『和漢三才図絵』が近眼鏡・遠眼鏡・虫眼鏡・数眼鏡の4種類の眼鏡を取り上げ、材料・構造・性能などを説明している。
2.江戸の眼科
1603年(慶長8)徳川家康が将軍となる。当時家康は眼病を患い、これを治療した渡来眼科医に薬礼として長崎出島に2万坪の地を与えている。このころから、眼鏡がオランダ・中国から輸入され始め1636年から1640年にかけて約6万個輸入され、米1升と同額であったと記録されている。
江戸時代は医師免許制度がなく、医術の心得があれば誰でも医師になり得た。一般的には、開業医師に入門し修業して免許皆伝を受けると独立した。受け取る報酬は医療行為の代価ではなく、患者の医師に対する謝礼であって、「薬礼」とか「薬代」と称した。しかも、その額は患者からの持参に任せたので一定ではなかった。江戸時代は内科医中心の医師社会で、眼科医はほとんど流行らず、眼薬売りと区別されなく、門には「めくすし」または「めくすりや」と掲げていたという。
江戸時代の眼科医として知られているのは、幕府最初の眼科医官に就任した渡辺立軒に、同様に幕府に召しだされた笠井重次がいる。元禄・享保時代(1688〜1735)に女医があらわれたが、眼科医の中に江戸の園女とか宮城の中目樗山の娘雲洞らが知られ、白内障の手術をしている。馬嶋流眼科は1357年に尾張薬師寺(愛知県海部郡)で再建し、1632年に後水尾天皇により明眼院の号を賜り、江戸期を通じて1日平均150人(1人約40日間の入院)の患者を擁した。江戸日本の眼科治療の中心として活動していたのであった。
従来からの中国眼科の治療法で眼科らしき治療がなされてきたが、1681年(天和1)に『眼目明鑑』があらわされて南蛮医学となり、蘭学による治療が行なわれてきた。江戸後期になると、『解体新書』を著した杉田玄白の息子の杉田立卿が父の解剖用語を用い『眼科新書』を著し、近代眼科の源流となった。その後、眼科医でもあったシーボルトが来日し、鳴瀧塾で眼科臨床学を系統立て講義したので、その高名を聞いて多くの人が長崎に遊学し、西洋医学を学び、地方に眼科学が伝わることとなる。
|
江戸中期の眼鏡屋もしくは眼鏡師なる職業は他の工人に比べれば非常に少なかったのではないかと推察される。虫眼鏡は用いられたかも知れぬが、掛眼鏡はもちろんのこと望遠鏡や顕微鏡は一般的に需要があったとは思えないからである。ここに、江戸時代の眼鏡商人を描いた喜多川守貞の『近江風俗志』があり、行商スタイルを見る。「その扮装三都相似たり」とあることから、全国的に共通していたに違いない。 したがって、これらのことから眼鏡商を専業とした者はきわめて少なく、他の業種と兼ねている場合が多かったといえよう。すなわち、数珠や鏡などを製作する傍ら、眼鏡レンズを磨いていたのであろうと推測される。販売を受け持つ眼鏡商も大方は兼業であったのであろう。 |
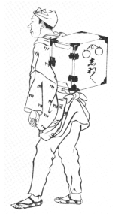 (文献1より) |
近世は都市つまり城下町の時代であった。近世城下町は、領主による兵農分離によって、あるいは地子免除という都市優遇政策によって巨大化し、繁栄していった。なかでも三都と呼ばれた江戸・京都・大坂は、幕府の直轄地として、その繁栄は目を見張るものがあった。江戸は百万人の人口を数える当時でも世界一の大都市であったが、人口の半分は武士人口で、この非生産的な消費人口を抱える巨大な消費都市であった。京都は、平安京以来の伝統をもつ美術・手工業生産によって立つ伝統都市であった。そして大坂は、「天下の台所」として、全国から物資が集まる流通都市であり、大衆必需品を生産する産業都市であった。これら三都で眼鏡を必要とする人々が数多く存在したことは十分に推測できる。
1755年(宝暦5)江戸幕府の命令で玉磨きの技術者を集めているが、これは御玉細工所を造るためらしく、文化・文政期になると「御眼鏡所」や「御眼鏡師」の名前が出てくる。1824年(文化7)刊行の『江戸買物独案内』の「め」の部には、
「 御眼鏡所「美濃屋平六本家 浅草駒形町 唐物類 紅毛物品等々
御眼鏡所 美濃屋又七 駒形出店 芝明神前 唐物類 紅毛物品等々
御眼鏡所 玉屋吉次郎 横山町 玉細工 唐物類 紅毛物品等々
御眼鏡師 美濃屋吉衛門 村松町 玉細工
御眼鏡師 美濃屋吉兵衛 池之端仲町 唐物小間物 硝子ギアマン
御眼鏡師 伊勢屋伊兵衛 尾張町 玉細工 」
とある。眼鏡商として専業で営業してはいなく、兼業スタイルで商う形であった。1692年(元禄5)の『諸国買物調方記』においても、
「 ▲京にて玉細工
目金 石おじめ 御幸町蛸薬師上ル下ル
▲江戸にて玉細工
南伝馬町一丁目 玉屋庄左衛門
神明前三島町 玉屋作右衛門
▲めがね師
京橋南四丁目 印判屋市郎兵衛
▲大坂にて玉細工
備後町 団扇屋忠兵衛
伏見町 八郎兵衛 」
とあって、眼鏡レンズを研磨する技術者の存在を示し、「眼鏡師」なる名称を使用している様をみてとれる。図のような眼鏡の看板をだす店舗を構えて眼鏡を売り、行商されていたらしい。
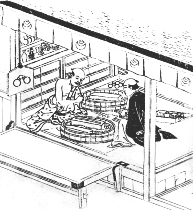

オランダ文化を積極的に取り入れる政策をとった田沼意次による政治下においては、
テレモメートル 寒暖計
テレスコープ 望遠鏡
ミクロスクープ 顕微鏡
ドンクルカームル 写真機
などが輸入されており、学問に恩恵を与えたことであろう。
これらの製品を作り上げるのに、ガラスレンズが必要となるは必然である。このガラスレンズについて、斎藤月岑の『増訂武江年表』の宝暦年間の記事に
「硝子は外国のものなるを、蘭人持ち渡り、長崎にて製することを得、京大阪に伝えしを、近頃東都に其の職人多く出来て、万の器を製し活業とする者あまたあり」
とある。この記事によって、江戸にガラス細工が伝えられたのは、京・大坂よりやや遅れたけれども宝暦の頃には、すでに江戸にてもギヤマン細工やそれを商売にする行商が相当数に上ったことがしられている。その中に、眼鏡師や眼鏡商が混ざっていたことのは推察できる。
眼鏡レンズを専業とし、巷間に名を知られた者に岩橋善兵衛がいる。『江戸時代の科学』に
「岩橋善兵衛は泉州貝塚の人、善兵衛は家業の魚屋を捨て、眼鏡の玉を磨いて販売するを業とした寛政5年より望遠鏡を製作した。伊能忠敬のために望遠鏡を製作し、彼に使用させた」
と叙述されている。伊能の地図は千分の一の狂いしかないもので、それに使用した望遠鏡は八角形の天体望遠鏡で、世界一と評されたオランダ製の望遠鏡に遜色のないものであったと言われている。したがって、岩橋善兵衛はわが国において、完全に近い天体望遠鏡を作った最初の人であるといえる。
幕末になると、ペリー一行が黒船で来航し、アメリカの文化にふれることとなる。通辞と称された通訳のかけていた眼鏡から蟀谷(こめかみ)まで伸びたフレームが流行るようになった。それまでは日本独自の眼鏡形式である支柱式天狗眼鏡に変化を与えることとなったのである。すなわち、頭痛押さえ眼鏡の出現である。
江戸時代の眼鏡業は、行商の眼鏡屋は別としてほとんど他の業種との兼業となっているが、眼鏡類の製造・販売がとうてい成立しなかったことを意味している。その理由は、眼鏡類そのものが、封建社会の性格上それほど要求されなかった実情に基づくであろう。
1.江戸絵画の中の眼鏡
日本における絵画の中で眼鏡が最初に描かれているのは、南蛮屏風(南蛮文化館所蔵)のなかの眼鏡である。南蛮屏風は来日した南蛮人を狩野派の画家によって描かれたもので、絵の中央で眼鏡をかけた宣教師は服装からイエズス会所属で、その手前の茶色の頭巾を被った人はフランシスコ会の宣教師である。
眼鏡の人をよく見ると、眼鏡が逆さまにえがかれている。画家の観察力不足か、記憶違いかもしれないが、眼鏡が希有な時代のあらわれであろう。眼鏡は鼻眼鏡と見える。


南蛮屏風と並んで祭礼風俗画がある。とくに「豊国祭礼図」には、眼鏡をかけた日本人を描いている。徳川黎明会所蔵のこの絵は、豊臣秀吉の七会忌の有様を描いたものである。
この絵の眼鏡は、祭礼という非日常的な場における、しかも仮装行列の中での異装として使われている。南蛮屏風に描かれたポルトガル人のように日常生活の中での使用とは異なっている。1604年(慶長9)当時では、眼鏡の使用はまだ少なかったといえるであろう。
|
美人画といえば喜多川歌麿と言われる彼の浮世絵の中にも眼鏡が描かれている「教訓・親の目鑑」という題目のシリーズにある。東京メガネ所蔵の絵には、眼鏡の左右のレンズ部分に「教訓」と「親の目鑑」と書いた眼鏡の絵がある。この眼鏡は日本独自のデザインである支柱式天狗眼鏡である。いわゆる紐つき・鼻あて式の眼鏡となっている。 18世紀後半の江戸の社会風俗をうかがうことのできるものに黄表紙がある。山東京伝の『孔子縞于時藍染』には、読書していた老人が眼鏡をはずして息子の申し出をきいている図がある。この眼鏡も、支柱式天狗眼鏡である。ちなみに、この小説のテーマは、天明の頃に老中に就任した松平定信が寛政の改革に乗り出し、倹約を奨励したのに対抗したもので、女郎買いに行くが散財できず、逆にお金を押しつけられたという話である。 |
 (文献1より) |
| 国立国会図書館所蔵の『天下一面鏡梅鉢』の中に、麒麟の見世物を見学する図がある。麒麟を見に来た見物人の中に眼鏡を手にもって見ている人がいる。耳にかける紐がぶらさがっているのが見える。これは多分近視用の眼鏡と推測できる。 | 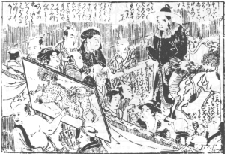 (文献8より) |
2.江戸文芸における眼鏡
滝沢馬琴の『馬琴日記』に
「林荘蔵、約束の厚眼鏡持参。代金壱両壱分の由也。しばらくかけ見、申す可く旨、申す聞け、則預かりおく。然れども、思うに似ずして宜しからず。衰眼実にせんかたなし」
とある。当時3両あれば1年間生活できたということを考えれば年収の3分の1にあたる代金の眼鏡となれば、最高級の品ともいえる。もちろん馬琴が売れっ子作家であるから、高額でもよいだろうという判断での値付けかもしれないが、高い代金の眼鏡を馬琴は使用していたことが、この記事から推測される。おなじく『馬琴日記』に
「お菊所望に付き、古眼鏡一枚、是れを遣わす。是れは天保の始めまで、我等年久しく用いたりしに、誤りて其の一玉うち破りしかば、別に安眼鏡の玉を入れ置きせし也。右の目見えざれば、一玉は飾りのみなれば、此の眼鏡、お菊眼に合い候由なれば、とらせたるなり。」
とあり、当時においては老眼鏡にては代々受け継がれている様相が判明する。
当時の眼鏡については、山口幸充氏による『嘉良喜随筆』のなかに
「目金ニスル水精ハ火取玉ノタチハ宜シ。常ノ水精ハ水ヲ吸ウユエニ、眼中ノ潤イヲ吸イテ悪シ」とあり、水精こと水晶が眼鏡レンズに引用されていることが判明するが、レンガ効能よりも字句からの印象のみで、水晶が眼鏡レンズに向いていないとしている点に、眼鏡知識への偏見が見られる。
井原西鶴氏の代表作の『好色一代男』の中には、
「清水や山あり多岐り茶屋もあり 亭の東に見る遠目がね」
という和歌が見られる。これは、清水観音では一文の拝観料で望遠鏡をのぞかせたいた商売があったことを和歌にしたためたもので、旅の御供に望遠鏡を持参したこともあることが『好色一代男』に記述されている。江戸時代の米相場は大坂でされていたが、東京と大坂間を手旗信号で符丁を送り望遠鏡で見て8時間で伝えたといわれている。箱根は早飛脚を利用していたそうである。大坂と広島間は40分で知らされていたというから驚きである。
3.江戸職人の眼鏡
眼鏡の国内生産が本格的に始まったのは元禄の頃であり、それに応じて眼鏡の使用も一般化したと想定できる。なかでも、細かい手仕事をする職人たちの中には、きっと眼鏡を必要とした人もいたであろう。江戸天保の頃の職人を相撲番付にしたものがあるので、参考までにあげておく。暇があったら探してみよう。ちなみにひらがな3文字で表現されている。
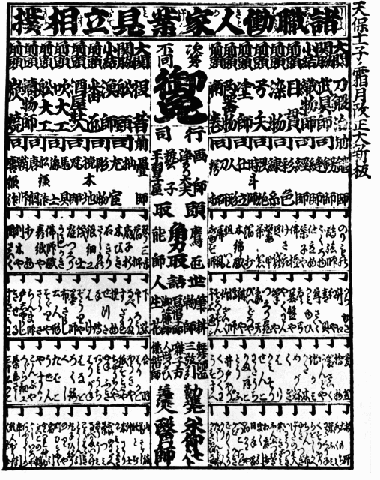
眼鏡姿の職人を描いた職人尽絵から見てみると、菱川師宣氏の手による1685年(貞享2)刊行の『和国諸職絵尽』に蒔絵師の図がある。
18世紀後半に至ると、橘民江氏の『彩画職人部類』には轆轤師の図がある。19世紀初期には、歌川広重氏による『宝船桂帆柱』に刀研師を見ることができる。
これら一連の職人尽絵から、相当の数の職人の中に眼鏡をかけた職人を見ることができる。細かな手作業をする職人の多くが眼鏡をかけて従事していたことであろうと思われる。
1.近代眼鏡製造の嚆矢!朝倉松五郎
明治維新から近代日本の出発となる。江戸城は宮城となり、年号は明治と改まり、1872年(明治5)には学制が公布され、新生日本が伸展した。眼鏡界も大きな動きを見ることとなった。1873年(明治6)朝倉松五郎の海外派遣である。河本重次郎氏の『眼科学』に
「眼鏡は羅馬希臓等にては全く未聞の器たり。千三百年頃に至り凸眼鏡出ず。16世紀の末に凹眼鏡出ず。日本にて洋式に従い眼鏡を作りしは東京四谷伝馬町朝倉松五郎を創めとす。彼は玉工たり、明治6年襖国博覧会あるに会し、彼地に至り翌7年1月、50有余の日数を以て眼鏡製造法を伝習し、其の帰国すねに当り機械一切官費を以て買収し、同年7月帰朝す。当時機械は内山下町博物局内に備え付け、彼は其の実験を命ぜらたり。其の際二三の弟子に伝授す。天明は人事を還りみず、彼は急死せり。享年34歳。」
とあり、朝倉松五郎のウィーン留学によって、機械によるレンズ製作が始められた。また、朝倉松五郎は、修得してきた眼鏡レンズ知識を『連珠師伝習録(別称は玉工伝習録)』を出し、日本における眼鏡レンズ製造の基礎となして眼鏡史上きわめて重要な資料となっている。
近代日本になって、このように眼鏡ことに近視眼鏡が大量に必要となったのは、教育の普及による文化の向上にともない新聞・雑誌・参考書などの図書類が続々と刊行され、小型になった活字に眼鏡の必要性が生じたからである。ところで、いまで言うファション的なおしゃれ眼鏡の伊達眼鏡が流行して、世の顰蹙を買うこともあった。
2.日本人の「眼鏡と出っ歯」イメージ発生の要因
幕末から明治前期の日本を描写した2人の外国人によって、「眼鏡と出っ歯」イメージの日本人が作り上げられている。すなわち、イギリス人のチャールズ・ワーグマンとフランス人のジョルジュ・ビゴーである。前者のワーグマンによって創刊された『ジャパン・パンチ』によって、眼鏡好きな日本人が描かれ、ことに1875年(明治8)の樺太・千島交換条約をテーマとする図から、日本人のイメージが形作られた。眼鏡と出っ歯の代表は榎本武揚で、これが日本人を描く基本絵となっていたことによる。
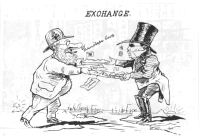 (文献8より)
(文献8より)ビゴーは、浮世絵の世界に魅せられて来日し、陸軍士官学校の雇い画教師を勤めた。そして、漫画雑誌の『トバエ』を発刊し、日本の習慣・風俗を風刺する漫画で好評を博した。代表作の『ビゴー日本素描集』のなかで多くの眼鏡をかけた日本人を描いている。
頭痛押さえ式の眼鏡フレームのツルの部分を長くしたスタイルのフレームの派生からツーポイントフレームの形へとフレームをみても大きな変化してきている。大正から昭和を経て平成の世の中に至までに、日本は幾多の試練を乗り越えながら、各界は躍進した。「眼鏡の福井」と言われるほど、眼鏡が福井県の目玉産業となったのは、1905年(明治38)増永五左衛門氏が福井市郊外の地麻生津にて眼鏡生産を始めたことに起因している。
大正時代に入ると、明治40年頃から試作されてきたセルロイド製フレームが生産されるようになる。第一次大戦後にはアメリカ映画が上映されるようになって、映画の中で登場する俳優のスタイルが風俗面に影響を与えた。絶えば、ハロルド・ロイドがかけていた眼鏡がロイド眼鏡と呼ばれ一世を風靡した。
昭和においては、戦前も戦後も幸か不幸かは別としてアメリカ風俗を濃く反映しており、機械化による眼鏡の大量生産と販売、各種新素材の開発とも相俟って、裾野をひろげている。第二次世界大戦終結で厚木基地におりたったマッカサー元帥のサングラス姿は日本国民に強烈な印象をあたえ、50年代にはマリリン・モンローのセルロイド眼鏡が流行し、60年代に入るとオードリー・ヘップバーンのトンボ眼鏡が流行り、太陽族のサングラスもしかり。近年では、幅広い層から支持を得て縁なしのツーポイントフレームが主流となっている。
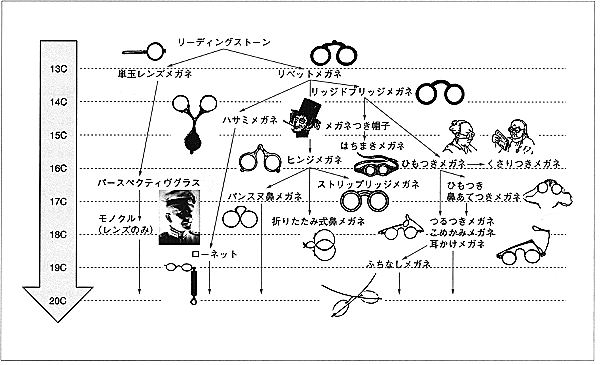
日本人の眼鏡保有率は総人口の約半分といわれており、高齢化による老眼鏡勢多制の増加、ライフスタイルの多様化などの要因で眼鏡装用者の増加や眼鏡ファション化が進展していくであろう。そんな中、眼鏡ユーザーに正確で快適な眼鏡が提供することを本分とした眼鏡作りに邁進してほしいものである。
参考文献
1.「日本の眼鏡」 長岡博男著、東峰書房
2.「ネガネのはなし」 藤田千枝著、さらえ書房
3.「メガネの文化史」 リチャード・コーソン著、八坂書房
4.「眼鏡の歴史」 大坪元治著、日本眼鏡卸組合連合会
5. 日本語大辞典、 講談社
6.「眼鏡レンズと検眼機器」 山田幸五郎著、日本レンズ工業協同組合連合会
7.「眼科学の歴史」、 眼科診療プラクティス(93)
8.「眼鏡の社会史」 白山晰也著、ダイヤモンド社