


| 眼鏡の日本伝来と変遷 |
| 西山 朝雄 M.S. Kikuchi College of Optometry |
ようこそ KCO E−ラーニング「眼鏡の日本伝来と変遷」にお越しいただきました。この講座は、「視力を矯正するために、目の前に装用するレンズを用いた器具(『日本語大辞典』)」と言われる眼鏡について、いつ頃・どこで・誰により考案され、それが、日本にいつ伝来して、どのように変遷したのかをエピソードを交えて進めて参ります。講座構成は2部構成とし、第1部は「眼鏡あれこれ」で、眼鏡の語源および目付き言葉のほかに欧米の眼鏡発展の歴史を取り上げるなど眼鏡の博物誌を取り上げ、第2部は「日本への眼鏡の渡来と発展」で、室町時代末期に日本に眼鏡がもたらされた時点からの歴史を説明しています。
この講座のテーマを理解するためには、基本的に学ぶならば白山晰也氏の著作による『眼鏡の社会史』(1990年 ダイヤモンド社)と赤木五郎氏編集の『眼鏡医学』(1996年 メディカル葵出版)が参考となり、長岡博男氏の手になる『日本の眼鏡』(1967年 東峰書房)やリチャード・コーソン氏著作で梅田晴夫氏訳による『メガネ博物誌』(1972年 東京書房社版。1999年に八坂書房から『メガネの文化史−ファションとデザイン−』として復刻刊行)も大いに教えられることが多いので、ここに紹介しておきます。この講座もこれらによって進めていますが、字数制限の関係で典拠明示してありませんので、疑問・質問があればこれらを調べていただき、なおかつ不明であればこの講座元に問い合わせくだされば、ご返答致してまいります。
Glasses または Spectacles と表現されるものが何故に眼鏡となったか?
日本へ眼鏡が伝来したのは、室町時代の末期である天文年間(1532〜1554)のこととされている。渡来品に眼鏡の名称を何故つけたのであろうか。眼鏡を手にした人物は、持参した人物に使い方を見様見真似で教えてもらい、眼鏡をかけてみるとよく見えたのであろう。この品物は目のように世の中が見えるものだということで、当時の言葉の「〜がね」とあわせて「目のような物」から眼鏡と名付けたらしい。名付け親は誰かと問われても、その行為を示す物証がないので、現在のところ推測でしかない。古語辞典で接尾語の「〜がね=当字の鏡=〜のようなもの」から「見えるもの=眼のようなもの」から眼鏡と表現したことは明白である。全国制覇を目指した織田信長が岐阜城に居たころ、外国から宣教師が布教許可を得にたびたび謁見しているが、その中に、眼鏡をかけた宣教師も多く会見したというから、織田信長が宣教師のかけている眼鏡に興味を持ち、眼鏡を自分の顔にあてて見たとしたら、たぶん「目がよう見えるがね」と言ったかも。さすれば、名古屋弁が語源となりえたであろう。
渡来した眼鏡を使用して、いろいろな言葉使いがされている。たとえば、中村幸弘氏が著した『日葡辞書の研究』に「Megane No Aru Fito 」とある。その意味は「見る物すべてを非常によく記憶する人」とある。日葡辞書は1603年(慶長8)イエズス会宣教師と日本人の協力で纏められ長崎学林から刊行された書物で、この時すでに眼鏡の語句が知られていたことを示している。
武田信玄と勝頼2代の事績によって軍法を説く江戸初期の軍学書『甲陽軍艦』に「太刀にも刀にも眼鏡と言うことに専一に候」と、眼識を高めよまたは目利きを高めよという意味に使われている。その後、眼鏡という語句の入る言葉として、「眼鏡が狂う」=物事や人への評価が間違っていたことをいい、「眼鏡に適う」=人から気に入られたり、実力を評価されたりすることをいい、「眼鏡違い」=人や物事が予想以上によくなかった場合に使われるし、「色眼鏡で見る」=物事を在りのままではなく、先入観で見ることつまり偏った見方をすること、のような意味で日常生活の中で眼鏡の語句を用いて表現するようになったのである。
眼鏡がつく事物に、「眼鏡揚羽」はトリバネチョウの仲間で、体長13cm ほどのもの。メガネトリバネとも。「メガネウラ」は、トンボによく似た史上最大の昆虫だったが、ジュラ紀に絶滅した。「眼鏡熊」は目の周囲に白い輪があり、南米アンデス山地に分布している。名古屋市の東山動植物園にても飼育されている。「眼鏡猿」は円形の目と耳介があり夜行性でフィリピンなどに分布している。「眼鏡蛇」はコブラ科の蛇で、有毒で首の後に眼鏡状の斑紋が特徴をもつ。「眼鏡絵」は凸レンズを通して見て透視遠近法を利用して見る覗き絵のひとつである。「眼鏡橋」は二連のアーチからなる石造りの橋で、長崎県の中島川に架かる眼鏡橋が有名である。
小説やTV・映画などに小道具として眼鏡がもちいられてはいるが、小説の題名につかわれているのは、管見のかぎり、島崎藤村氏による『眼鏡』しかない。実業之日本社より愛子叢書第一編として大正2年2月に発行された小説である。その内容は、
「眼鏡がこんな話を始めました。
私はもと東京の本郷切通坂上にある眼鏡屋に居たものです。その眼鏡屋の店先に、他の朋輩と一緒に狭いところへ押し込められて、窮屈な思いをして居りました。そして毎日欠伸ばかりをしながら、眼鏡屋の隠居が玉を磨る音を聞いて居りました。・・・・」
という書き出しで始まる小説で、主人公がこの眼鏡を購入した後、ともに関西旅行に出かけ刀鍛冶に出会うという話になっており、時おり眼鏡から見た印象を擬人法によって述べさせている。
閑話休題1 目のつく諺にふれてみよう
1.眼鏡の原始的形態
アラスカのクスキナックやブリストル湾地方のエスキモー人は、木製の木片に横裂孔をうがったイヌイトで、風雪と遮光を避ける民具としている。
古代日本には、ことに縄文時代から弥生時代にかけて、人間を形どる土製品が製作されていた。これを土偶という。図をみると、目がひときわ大きく形作られていて、イヌイトに相似している。乳房と骨盤形態から女性像と推定され、眼鏡形のも当時の民具と推定されている。ちなみに、矢追純一氏にいわせれば、未確認物体のUFOであると言う。なお、仏教の修業者を形どったものを羅漢というが、各地の寺院には眼鏡をかけさせたものが見当る。注意して探してみよう。



2.レンズの原理発見
光は宇宙の創造とともに出現し、人類はレンズを発明した。
「光は東方よりきたる」という格言や、『旧約聖書・創世記』には「初めに神は天と地を創造し、光あれと言われた。すると光があらわれた」とある。「色彩論」でニュートンに対抗したドイツの哲学者ゲーテは、臨終の言葉として「もっと光を・・」と言い残している。
眼鏡の原理は、レンズによって近視または遠視を補正することにあるが、人類が最初に発見したのは、凸レンズを透して物体を見ると、物体が拡大されて見えるという方法であった。
ガラスは、西暦紀元前8〜9世紀頃に古代カルタゴ・エジプト・ギリシア・ローマ時代の遺跡から発見されている。これらは、日本神代の曲玉=勾玉のように主に男女の身辺や器具等を飾る装飾を目的に作られていたようである。
ガラスの製法に関して、ローマ帝国初期の海軍提督で学者であった大プリウスの著書『博物誌』に「東地中海に面して地で、商人達が夕食の支度をするために、海辺の白砂の上で天然ソーダの燃料を盛り付け煮炊きをした。翌朝、キラキラした光る物体があった。それは、半透明のガラスの固まりであった」というエピソードが載っている。
水晶やガラスで凸レンズ状の玉を太陽にあてると、その焦点の燃焼物に火がつくというのが凸レンズの原理である。この原理は、「人間はポリス的動物である」と主張した古代ギリシアの哲学者アリストテレスの研究にその理由を述べる。降ってローマの哲学者セネカは、水を満たした透明なガラス器を透して見る物体は拡大して見えるという理論を述べている。これらが、レンズの原理を述べた初期の記録である。
3.初めての眼鏡か?
皇帝ネロ(BC37〜68)が緑玉つまりエメラネドによる眼鏡を用いたと言われている。前述の『博物誌』のなかに「ネロは闘技場で剣闘士の試合を見物する際に緑玉を使用した」とか、スウェトニウスの『ローマ皇帝伝』のなかで「ネロの瞳は碧く、視力が弱いため物を見るときは目をしかめた」ともある。ポーランドのノーベル賞作家シェンケビッチが、その受賞作『クォ・バデス』の中で、皇帝ネロが緑玉をレンズ替わりに眼に押しあてて、キリスト教徒が猛獣に噛み殺されるのを食い入るように見入っていた、とも書いている。
4.光学理論の変遷
光とは何か?あるいはレンズに関する知識は、天動説の創始者プトレミーによると言われる。光学に関する法則を発見し、アラビア文化へと発展した。アラビアのアルハゼンは光学理論は勿論のこと、注目すべきは眼球の構造に関して角膜・水晶体・硝子体・網膜 などを明らかにし、「眼から外界に視光線が投射され、見えるという現象が起こる」を「外界から眼球に光線が入射することにより、ものが見える」としたことは重大な発見と言える。
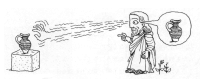
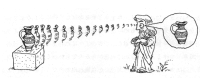
1.眼鏡の発明者 イギリス説とイタリア説があります。
【イギリス】ロジャー・ベーコン(1214〜1294) (文献2より) |
英国修道士で驚異博士と称せられていた。 彼の残した記録文書に 「水晶やガラスのかけらを通して文字を見ると、文字は大きくはっきりと見える」 とあり、凸レンズの拡大力について述べている。 当時の社会状況は、中世キリスト教の時代で、「神の与えたもうものに逆らうな」精神が充満しており、彼の行為は神を冒涜することになり、逆評価され投獄され獄死した。よって、眼鏡の発明者とはいえないかも。 |
【イタリア】その1 サルグイノ・アルマテー(1317年没)
墓碑銘に「此処にフローレンスのアルマテー家のサルビー眠るメガネの発明者、神よ彼の罪をゆるしたまえ」とある。
その2 アレキサンドロ・スピーナ(1313年没)
ピサの聖カタリーナ修道院の年代記のなかに「彼は誰かが作って、誰にも教えようとしなかった眼鏡を自分で作った。そして、それを進んで人々の間に広めた」とある。
1305年のジョルダン・リバルトの説教に
「視力を回復させる眼鏡の技術は、発明されてから20年も経ていない。」
とあり、このことから 1305−20=1285年ころ と推定できる。この裏付けとしてサンドロ・ポポゾの『家庭経営論』の中に
「私は年をとって視力が衰えたので、眼鏡と称するガラスなしには文字を読むことも書くこともできなくなってしまった。」
とあり、眼鏡発明年の推論根拠となっている。
要するにエジプトのカイロで究明された眼鏡の原理がヨーロッパ諸国に伝わりベネチアのガラス工業と結びついて、眼鏡なるものが製造され、その商品を行商人の手によりドイツ各地にさばかれ、それがヨーロッパに広まったといえよう。
【参考1】中国の眼鏡=アイタイと称したという
マルコ・ポーロの『東方見聞録 』は1298〜99年に完成したが、中国眼鏡つまり=支那眼鏡 のことが表記され、歴史あるものという。調べて見る価値があり、研究がまたれている。
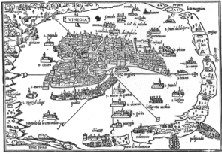 (文献2より)
(文献2より)
 |
レンズ豆の模様のガラスを「ガラスのレンズ」と称す ↓ レンズのみ使用 |
2.眼鏡の形状の歴史
参考資料の一つがイタリアのトレピソのセントニコラ寺院にあるトーマス・モデナ作による老人像で、眼鏡史上において有名である。いわゆる鋏眼鏡をかけている。
 (文献2より)
(文献2より)
眼鏡は、元来、拡大鏡から発達したものであるが、手にもって使用しているうちに縁がつけられ柄がつけられ、2個併用の形になるまでには長い期間を要した。
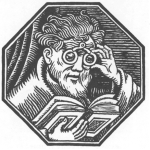 (文献2より) 
|
単眼有柄が、眼前固定となったのは14世紀から15世紀初頭であり、15世紀中期にドイツのグーテンベルグにより印刷術が発明されてから、印刷物が出回り読書階級が増大して、眼鏡が貴重品的存在から一般的実用品となり、眼鏡は発展した。 ドイツのニュールンベルグに最初の公式規則による眼鏡工の誕生も1483年であった。この頃になると、イタリアのベネチア・ミラノなどのクラウン・フリントグラスが使われて、優秀なレンズが作りだされた。フレームの鼻の上に手でささえて乗せる形状の鞍型となり、レンズも丸型から楕円型が用いられている。 現在のような耳掛け形は、1623年頃にスペインではじまったといわれ、こめかみ辺でとめていたものが、段々延びたのである。 |
発明家ベンジャミン・フランクリンが二重焦点レンズを考案し、みずから使用したのが1760年であった。彼は、生涯を祖国の独立と開拓に捧げ、奮闘努力した立志伝中の人物である。政治家・外交官・物理学者のほかに眼鏡光学者としても知られる。二重焦点レンズの眼鏡を使用したのは、50歳のときで、友人への手紙の中で、「私は眼鏡を二つ持ち歩いていました。掛け替えが面倒なので、レンズを半分にして一つの枠にはめこんで使用しています」と利用事由を述べている。
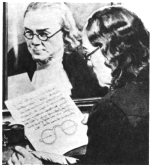 (文献2より) |
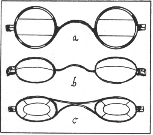 (文献3より) |
1.眼科医の眼鏡意識
歴史的には、西洋の眼科医は、眼鏡の使用には賛成ではなかった。
1285〜1307年にフランスのマントペリアの医学校で眼科を教えたバーナード・ゴードンはコリーリウムを使用すれば眼鏡は不要だといい、同校教員のガイ・カルアックも目薬が効かない場合に眼鏡をもちいるべきと教えた。
16世紀中頃、最初の科学的な眼科医とされるジョージ・バーチェでさえも目は眼鏡使用で悪くなるといっていた。1840年には、シチェルは遠視用の凸レンズは禁止されるべきといい、1855年のジャージーは眼鏡をかけるという狂った習慣はいくら諌めてもし過ぎることはないとまで言っている。多くの人々の間において、レンズは目を弱めると思わされ、その恐れは今も続いている。
眼科医の黄金時代に、ハーマン・ヘルムホルツは 『生理光学』という著作で視力系統や光学的特性に貢献した。フランク・ドンデルスは視力調整や屈折変異についてのテキストを発行した。前者は人間の視系統の理論の理論的基礎となり、スウェーデンのグラッフェが研究を固めた。後者は臨床への応用の科学的根拠を与え、明治天皇の侍医となった日本人の伊藤玄伯がこの説を広めた。
この2人は多くの眼科医に眼鏡をあわせるように提唱したが、視力アップのための眼鏡の使用をほとんどの眼科医が賛成しなかった。この期間が長かったことから、オプティシャンが眼鏡をあわせることになり、オプトメトリーが認められ、信頼されることとなったともいえる。


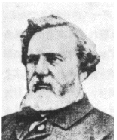
2.検眼機器の発達
ドイツの眼科学者ハーマン・ヘルムホルツ〈1821〜1894〉は検眼鏡を発明し、角膜湾曲を測定するオフサルモメーターも発明して、近代眼科学の分野で大きな足跡を残した。
アルベール・グルストランド〈1862〜1930〉は、眼の屈折を計算する模型眼を作成し、スリットランプ=細隙灯を作成して、眼科では初めてのノーベル賞を受賞している。
レンズの度を、現在用いている「ディオプトリー」に提唱したのは、ドンデルスとドイツのナーゲルである。また、世界的に使用されている視力表のなかにあるランドルト氏環はスイスのエドモンド・ランドルトである。
日本式の視力表は、石原忍が作成し、彼は世界で一番よいとされる色盲表も作成している。また、新カナ文字の提唱者でもある。
1.眼鏡の形状変遷
眼鏡をどのように眼前固定するのかが懸案の的であった。『ユートピア』を著したトーマス・モアは肖像画に見るような鼻の上に固定する眼鏡を使用していた。

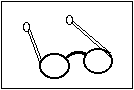
1730年 ロンドンの眼鏡商エドワード・スカーレットがテンプルの先端にちいさな輪をつけた蔓<つる>付き眼鏡を考案している。
1760年 イギリスのベンジャミン・マーチンなる眼鏡商が技術専門書を出して宣伝している。すなわち「ビジュアル・グラスは目の原理や視力の法則に則って作成せねばならぬ」。これを売出しところ、大いに話題を呼び、版を重ねたという。
遠近両用眼鏡は多焦点レンズ(マルチ・フォーカス)タイプが現代市場を独占しているが、その前身は二重焦点レンズ(ダブル・フォーカス)タイプで、最初に考案したのは前述したベンジャミン・フランクリンというのが定説となっている。
2.コンタクトレンズの発想
日本の江戸時代の忍者は、盲人のごとくに見せ掛けるために、鯉の鱗を目中に入れる修業をしたという。コンタクトレンズの走りと考えられる。
コンタクトレンズは、1830年頃にイギリスのハーシェルが考えだし、1928年ドイツの眼科医ハイネがコンタクトレンズの基礎となるレンズを作り上げている。19世紀末、スイスの医師オイゲン・フィックがレンズを用いた研究成果を発表し、初めて「コンタクトレンズ」の言葉を用いた。これが契機となり、コンタクトレンズの実用化に取り組まれたが、成果が実を結んだのは半世紀を経た第二次大戦後で、プラスチックの素材が開発されたのが、今日の隆盛の元となった。
その後時代を経て、アメリカのウェスリーがスフェリコンレンズを完成してから次第に普及しはじめチェコスロバキアで含水性の素材が開発されると、ハードからソフトへさらにはディスポタイプが登場して現在に至っている。
日本のコンタクトレンズの開発は、「目にコンタクトレンズ」を社名にしたメニコンによってなされたといえよう。
3.眼鏡と物理光学
光学の分野は、眼鏡と眼科双方に密接な関係がある。眼鏡の出現から500年の歳月を経て、光の解明と眼球の生理機能が注目された。
光の本質は波動であると説いた『光についての論考』を著したのがオランダのホイエンスであった。これに対し、『光学』をもって光は粒子であると唱えたのがアイザック・ニュートンであった。彼は反射式望遠鏡を初めて製作した人物でもある。
ニュートンが活躍した100年後に、人間の視細胞は赤・青・緑の三色に反応するという「三原色説」を唱えたトーマス・ヤングがイギリスに登場する。フランスでは「フレネルレンズ」を考案したオーギュスタン・フレネルが出て、光は横波であると主張した。
光の論争に決着がついたのは20世紀にはいってからのことで、アインシュタインが光量子説を唱え、ドイツのプランクが「量子論」を開拓して、光が粒子と波動双方の性質を持っていることが証明された。ドイツでは、ヨセフ・フラウンホーファーがレンズの屈折率を測定し収差を取りのぞき製品の改良に努め、プリズム分光計を製作し屈折望遠鏡を設計した。彼はドイツ光学界の祖といえ、カール・ツァイスやローゼンストックが続いている。
眼科関連に目をむければ、ハーマン・ヘルムホルツは眼底の観察つまり乳頭・網膜・血管などが見える検眼鏡つまりオフサルモスコープを発明している。このころ、「コ」の視力表を考案したのはオランダの眼科医スネレンであった。乱視用眼鏡レンズは、1813年に円柱レンズがシャンブランによって工夫され、1830年頃にジョージ・エアリーが円柱レンズを実用化させ、1840年頃になるとトーリックレンズがススチピによって試みられたという。
閑話休題2 目のつく言葉を知ろう。